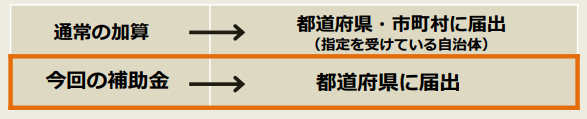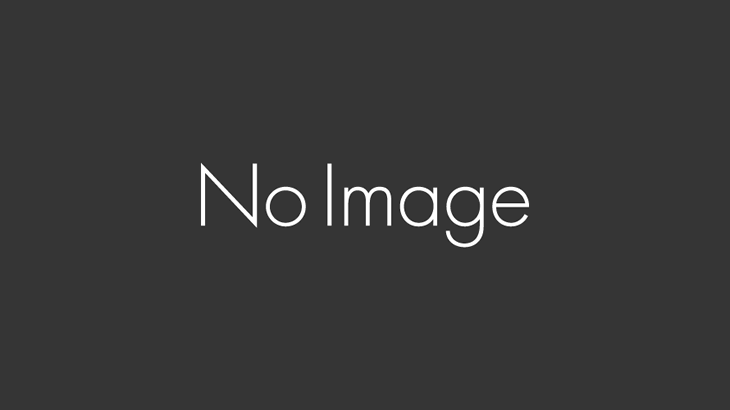久留米リハビリテーション病院 抱え上げないケアの風土化を
久留米リハビリテーション病院(福岡県久留米市、柴田元院長)は、ケアでの安全確保や職員の腰痛予防だけでなく、リハビリテーションの質の向上のために、抱え上げないケアの理念を徹底し、法人として組織的にリフトを活用する。柴田院長とリハビリテーションセンター副センター長の今村純平さん(理学療法士)に話を聞いた。
中心スタッフが育ち徐々に浸透
このため、病院の浴室にリフトを1基設置し活用を促したが、その後も半年から1年間はだれも使わなかった。
それでも抱えないケアが、患者・職員をともに守り、ケアの質を高めることを現場へ発信し続けた。次第に中心となるスタッフが育ってきたこともあり、数年後にようやくリフトが病院内で浸透するに至った。
経営者の覚悟と人材教育が重要
当院では毎年、新人教育としてリフトやスライディングボードの活用を徹底して指導する。トラブル事例の共有や、ベッドサイドに移乗時のチェックリストを置くなど対策を欠かさない。
これまでも各地から当院に多くの見学者が来たが、全国でリフトはあまり普及していない印象だ。設備投資が高額な上に診療報酬上での評価がないため、経営者が現場で直接リフトの効果を見て、ケアや人材確保の観点で有効性を確認し、覚悟を決めて導入するしかない。
リハビリの質向上のためにもリフトを活用
二つ目の理由として、機械を使った介護への抵抗感がある。
三つ目の理由は、日本人が小柄なため、抱えようと思えば抱えられる点があるかもしれない。
当院には、体重が100kgを超える患者(最大167㎏)も紹介されてリハビリに来るため、転倒など様々なリスクも大きい。リハビリ室に天井走行型のリフトを導入したのは、患者とスタッフの安全を守りながら、リハビリの質を高めたかったからだ。
現在、重度障がい者の増加に対応するため、各病棟の観察室・個室に天井走行型リフトのレールを追加整備する準備に入った。患者の増減に合わせて、吊り上げを担うハンガー部分を適所で使いまわせば、設備費用が省けることも期待される。
明確な目標設定がリハビリのモチベーションに
その中には、自宅で転倒し脊髄損傷で寝たきりとなった肥満患者に対し、リハビリを行うことで、徐々に歩けるようになり、日常生活が自立レベルとなった後、正職員雇用につながったケースもある。
自分の社会での役割を自覚することも、リハビリのモチベーションを高く維持する上で大切だ。
抱え上げない介護と早期リハビリの定着を
現状では、交通事故などで全介助状態となった患者が、ケア不良のため廃用が進んだり、褥瘡ができた状態で、紹介されてくることがある。
リフトケアが普及し、亜急性期から維持期にかけて、より安全で有効なリハビリやケアが実践されることを期待し、この取り組みを続けていきたい。
施設では風土として定着
「教える側に回ろう」を合言葉に、院内での抱え上げない介護が風土として定着している。
移乗をコミュニケーションの場に
人の手で抱える場合、脇の下などに局所的な力がかかって皮膚を損傷したり、場合によっては骨折を起こすこともある。介助される側も、身構えてしまい身体がこわばる。
リフト活用のメリットは、介助者の技術をある程度標準化すれば、必要以上に患者に密着せず、談笑しながら移乗できるほど、利用者・介助者双方にとって負担が少ない点だ。
「移乗はコミュニケーション」と言えるほどメリットが多い。
リハビリ、在宅復帰にもリフトを活用
また、在宅復帰支援のために、家電の操作をタブレット一つに集約したり、自宅の天井にリフトを設置して、一部屋で生活が完結するワンルームリフトケアの提案も行っている。介助者の負担軽減と本人の自由度の向上により、離床時間の延長など良い結果が得られている。
介護の質担保のためにもリフト活用を
当院では、全職員がリフトを活用できることが自慢であり、今後も、患者家族を含めて福祉用具を活用した、抱え上げない介護を風土として広めていきたい。