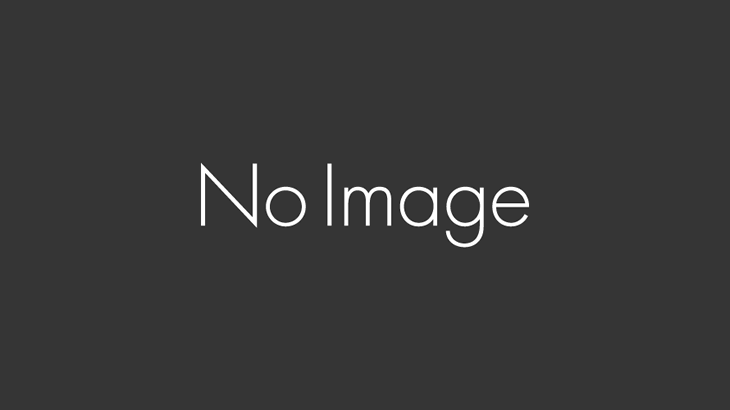最期まで妻を思い続けたTさん
正月明けのこと、数年前に認知症だった奥さんを看取った小規模多機能事業所「ひつじ雲」の利用者T氏が、住み慣れた自宅で、親族やひつじ雲の職員が見守る中、穏やかな最期を迎えた。
食事会に参加し始めた当時から、T氏の奥さんには認知症の症状があった。T氏はすでに奥さんの介護を始めていたことになる。しかし、食事が終わったあとに奥さんが「多摩川」という唄を歌ってくれた姿は今も忘れられない。
その時の話の内容がとても印象深く、夫婦の絆の強さを感じた。奥さんが「あんたのことは私が最期まで看るからね」と常々語っていたという。その奥さんが認知症と診断され、子供のいないT氏は「当時、僕は誰の手も借りずに彼女を介護すると覚悟した」と話していた。
その後ひつじ雲を利用して5年半が過ぎ、肺炎と診断され自宅療養となって1カ月が経ったころ、夫らが見守る中、自宅で静かに息を引き取った。
いくつかの病気と向き合い、定期的な検査入院もしていた。親族や在宅医からは「そろそろ施設入所がいいのでは」と勧められていたが、本人の「ひつじ雲さんの助けを借りて、妻の仏壇を守りたい」という思いは揺らぐことはなかった。
昨年からは転倒を多く繰り返すため、ベッドそばにポータブルトイレを設置し、住宅改修を行い、訪問看護や往診の点滴加療を始めた。室内移動は車いすで行っていた。小多機の看護師は医療関係者との情報交換を密にして、職員たちと情報共有した。
点滴を行うと、落ち着いて会話ができるようになったが、再び呼吸に変化が表れた。医師の「数時間ですね」の言葉通り、1時間後に皆が見守る中、穏やかな最期を迎えたのだった。T氏は最期まで奥さんがいる仏壇を守り切り、最愛の人と二人でいることの価値を示し、教えてくれたように思う。