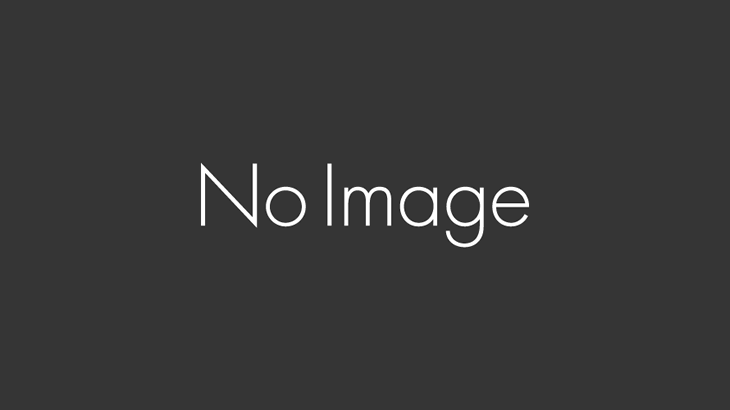おうちにかえろう。病院「『自宅で最期まで』のあり方を示す」
今年4月、東京都板橋区に開設した「おうちにかえろう。病院」(定員120床)。やまと診療所で在宅医療を展開する医療法人社団焔(ほむら)(安井佑理事長)が運営を手掛ける。なぜこれまで在宅医療を専門にしていた同法人が病院運営に至ったのか。水野慎大院長に話を聞いた。
ただ、患者や家族が在宅での暮らしを望み、我々もそのために力を尽くすものの「入院して自宅へ戻って来られなかった」ケースはやはり存在する。その課題をクリアするための手段として行きついたのが、この「おうちにかえろう。病院」の立ち上げだった。
名前の通り、従来の病院医療に加え、自宅に帰って自分らしく生活できるような支援を行う。例えば、服を持参してもらい、朝は普段着に、夜はパジャマにと1日2回着替えてもらうことを推奨している。病衣より、普段着のほうが患者同士の交流も生まれやすい。食事の支度や服薬もできる限り自身で。リハビリも通常の機能訓練も行うが、隣接するスーパーに買い物に行って調理してもらうなども練習する。入浴はそれぞれの自宅に近い入浴環境を再現する。ADLやIADLを確認するためでもあるが、患者本人や家族に自宅に帰ってからの生活をイメージしてもらうのが目的だ。
「関わることでの患者の変化」が自信に
正直にいえば、私もここまでの状態となると在宅復帰は難しいかもしれないと考えていたが、ある時、看護師が好物のいちごを見せるとAさんが反応を示すことを発見した。普段のAさんは発語もなく、目線も合わずに意思疎通ができない状態だったが、いちごを見せると目を見開く。その日から職員のAさんへの関わり方は大きく変わった。頻繁に声を掛け、まだ食べられはしないがいちごを見せたり、口に当てて刺激を与えた。当初寝たきりだったが、まず起きられるようになり、2週間ほど経ったころにはわずかに口を開けていちごを食べようとする反応がみられた。「これは本当にいけるかも」と皆が思うようになり、食形態など試行錯誤を重ねてひと月後にはペースト食を口から食べられるようになった。発語がみられてからの回復は早かった。話し始めると、飲み込む力もかなり回復してくる。一時帰宅などを挟みながら、最終的には全量を経口摂取できるまでになり、退院前日はお笑いのDVDを見てげらげらと笑っていた。
この成功体験は、我々にとって大きな自信に繋がった。「関わり続けることで、患者がここまで変わる。在宅に戻れる」ということを知り、この患者にもAさんにとってのいちごのような「きっかけ」が何かあるのではと注視するようになった。
「安定経営でなければ広がらない」
しかし、経営的に安定していなければ、いくら取り組みがよくても後には続いてもらえない。この半年の実績で10月から地域包括ケア病棟に転換した。入院だけでなく、いずれは外来も開始する。在宅医療の実践と安定経営を両輪に、在宅医療のあり方の一つを示していけるように努めていきたい(談)
(シルバー産業新聞2021年11月10日号)