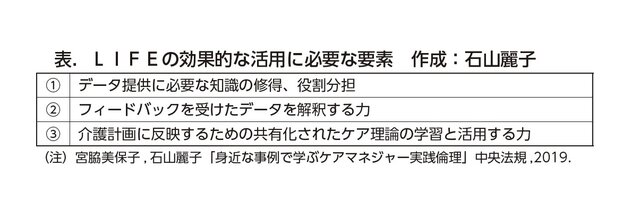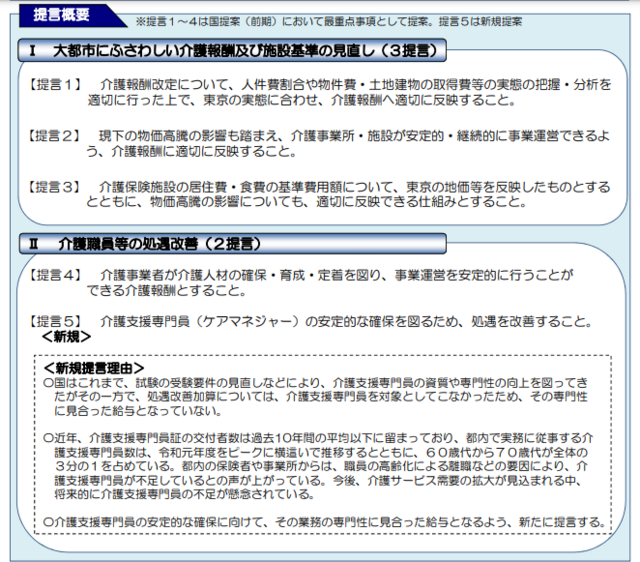思い出を置き土産に旅立ったT子さん/柴田範子(連載117)
1カ月前、急激に体調を崩したT子さん(95歳)が、自宅で娘さんに見守られながら旅立った。 小規模多機能「ひつじ雲」に通うことが難しくなったT子さんの自宅へ、介護職員や看護師が毎日訪問を繰り返していた。
点滴を外したという報告を聞いて、お迎えは近いなと思った。時間が取れた日の午前中に、「T子さんの所に行ってきますね」と職員に伝え自転車で出かけた。事前に連絡しておいたためか、チャイムを鳴らす前に娘さんが玄関を開けて迎えてくれた。「母が喜びます」と言う一言に、なぜか胸が熱くなった。
.
目の前に横たわっているT子さんは、目を閉じて身動き一つしない。ひつじ雲の看護師から聞いていたように、右の方に首が拘縮しているようで痛々しい。約1カ月間、週3回の点滴のみが施されていた。食べ物を欲しない。口に入れても誤嚥する可能性が大きいためという理由が挙げられていた。
これまで看取ってきた方々の最期に向かう姿を、どのように表現するのが良いか考えていた時期であり、一つずつ手放していくという表現に、「その通りだ。とても自然でいい表現だな」と受け取った。
日本国籍を持たないT子さんの父親は、母国で日本語を覚え、医者になりたくて来日。迎えてくれた先では仕事が忙しく、勉学の時間が十分に持てなかったようだ。医師をあきらめ、自動車関係の仕事に就き、かなりの収入を得るようになったという。のちに中華料理店などを開き、順調だった時期が何年か続いたそうだ。
その時代のT子さんは、「女学校で英語を教えてくれた教師が大好きで、誰よりも懸命に勉強したのよ」と、ひつじ雲の中で得意げに語っていたことを思い出す。イギリスから医療・福祉関係の方々が見えたときも、英語で堂々と挨拶していた姿を思い出す。
外車を乗り回したT子さんは、母親とは双子のように仲が良く、どこへ行くにも一緒。そして、本好きは生涯変わらず、入院した時も書名を娘さんに伝え、何冊も持ち込んだそうだ。筆者の読み終えた本を「読みますか」と手渡すと、ひつじ雲でも自宅でも「借りてきたよ」と言って、遅くまで読書に耽っていたようだ。娘さんは、母親とのやり取りを懐かし気に語っていた。